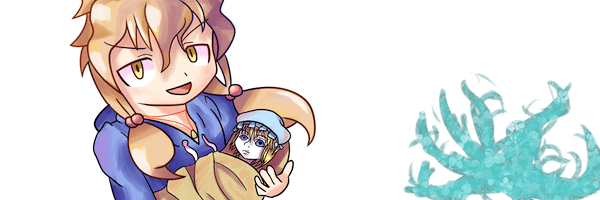【Halloween】ハロウィン会場にて
パーティ会場の片隅で、私の手は黙々とテーブルに並べられた食べ物を口に放り込んでいた。左手でフライドチキンを握りしめ、右手でアルコールのないハニーエールをぐっと流し込む。飲み干したグラスをテーブルに叩きつけるその様子は、酒に酔って怒り上戸になったように見えたかもしれない。
辺りでは子供がお菓子を求めて騒いでいる。大人たちはそれに答えてお菓子を与えたり、あるいはそれを拒んで悪戯されたり。中には本当の化け物と見分けのつかない姿に化ける冒険者もいたりて、会場内は混沌としていた。数分前までは、私もあの騒ぎの中に紛れていた。私のポケットの中に入っているいくつかのお菓子がその証拠だ。だが、それも今となってはもう昔の話。機嫌を損ねた私にはあの輪の中に入っていく気など怒らなかった。
元々、この会場自体に期待をしていたわけではない。私の目的は、この日に『あちらの世界』からやってくる、どこかの誰かの先祖の霊や、悪霊たちだ。悪霊を退けるために仮装をし火を焚くこの会場内で、獲物となる死霊と出会えるとは思っていなかった。悪霊とは言え元は人。人の集まるところに寄ってきて、火の回りを飛び交う虫のように人だかりの近くで狼狽える。そんな風に会場から少し離れたところで、ふらふらと彷徨う悪霊を刈り取るつもりでいたのだ。会場で子供のように振る舞うのはただの冷やかし。それがまさか、こんなに会場内に霊魂が跋扈しているとは思っていなかったのだ。
この会場は既に他の死霊術士のテリトリーになっていた。と、私は認識した。辺りを飛び交う色とりどりの光を放つ霊魂を見れば、幽かに他の術者の”臭い”がする。このパーティのスタッフの中に同業者でもいたのだろう。
その霊魂の動きをじっと見つめていれば、彼らはまるでそれぞれが独自の意志を持っているかのように参加者をもてなしている。これだけの霊魂を統率し、なおかつ指を動かすように躍動的に操る。一体どれだけの技量をもったネクロマンサーがここを牛耳っているのだろう。別にそのネクロマンサーが怖いわけじゃないが、その力量には目を見張るものがある。
それを考えると、何時までもここにいたところで、私にメリットはない。会場内が支配されている以上、それ以外の場所で、できるだけトラブルを起こさない距離で活動しなければ。別にそのネクロマンサーが怖いわけではなくて、人のテリトリーを踏み荒らすのは趣味でないというだけだ。ここは一旦会場から退いて、街中に飛び込んできた悪霊を狩る方が賢明だろう。テーブルに残された最後の品物であるカボチャのパイに、私の手が伸びる。
その顔だけ拝んでおいても良いのかもしれないが──そんなことを考え、否定するようにそのパイを一気に口の中に詰め込んだ。他のネクロマンサーと交流して、新しい方式の知識を得るのは悪い話ではない。だが、今感じた力量差でそれを行う必要性もない。ある程度目線の高さが合うところになってから。対等な立場になってからで良いじゃないか。別にそのネクロマンサーが怖いわけじゃない。
一言メッセージ上に
「E-No.13 バラーさん の【ジャックのハニーエール】【南瓜鶏のフライドチキン】」
「E-No.45 ルタちゃんの飛ばす霊魂 とカボチャパイ」
をお借りしました!
あとルタちゃんの力量を見誤った上で一方的にビビりました!